1.保昌山の創建(ほうしょうやまのそうけん)
🌿 創建の時期
保昌山が創建された正確な年代については、他の山鉾(やまほこ)と比べて明確な記録が残されていません。しかし、歴史的な背景や関連する文献をもとにすると、**嘉吉元年(1441年)に足利義教(あしかが よしのり)**将軍の命により、多くの山鉾が新たに創建されたり、過去のものが復興されたと考えられています。この時期は、室町時代の中でも特に祇園会(ぎおんえ)の盛り上がりが見られた時代であり、保昌山もこの祭りの流れの中で生まれたと推測されています。
保昌山の創建は、単なる偶然の産物ではなく、当時の社会背景や文化的な変化を反映したものであるといえます。室町時代には、武士階級の力が増し、同時に文化的な活動も盛んになった時期であり、こうした背景が保昌山の創建にも影響を与えたと考えられます。
📜 文献に見られる記録
**八坂神社(やさかじんじゃ)**の記録である『祇園社記(ぎおんしゃき)』第十五巻には、祇園会に関する詳細な記述が残されています。その中に次のような記録があります。
一、花ぬす人山 五条東洞院と高倉の間
この「花ぬす人山(はなぬすびとやま)」が、現在の保昌山を指しているとされています。この記録は**応仁(おうにん)**の乱(1467年)後、祇園社家(ぎおんしゃけ)の飯加清彦(いいか きよひこ)が自身の記憶に基づいて筆記したものであり、嘉吉元年から応仁の乱までのおよそ30年間にわたって巡行していた山鉾の名前を列挙したものです。
この記述から、保昌山の創建が応仁の乱以前に遡ることはほぼ確実とされており、その起源は嘉吉元年の創建ブームの中に位置づけられています。この時期に創建された山鉾は、当時の社会的・文化的な影響を色濃く受けており、保昌山もその一例といえるでしょう。
🌸 花盗人山の由来
山鉾のデザインやテーマは、その創建当時の社会の価値観や思想を反映しています。**室町時代(むろまちじだい)**に存在した63基の山鉾のうち、およそ3分の1は歴史的な物語や神話をモチーフにしていました。こうしたテーマは、当時の人々が過去の偉業や伝説を称える文化的な風潮を示しています。
一方で、保昌山は**平井保昌(ひらいのやすまさ)**という武士の逸話に基づいています。保昌は、歌心に優れた武士として知られ、ある夜、愛する女性に対する思いを証明するために、**御所(ごしょ;天皇の住まう場所)**の南殿から梅の花を盗み取ったという伝説が語り継がれています。
この物語は、他の山鉾とは異なるロマンチックで風流なテーマを持ち、その独特な趣向が多くの観客の興味を引きました。そのため、この山は「花盗人山(はなぬすびとやま)」とも呼ばれるようになり、しばらくの間、「保昌山」という正式な名称よりも親しまれていたことが文献からも読み取れます。
🏠 所在地の変遷
最初に花盗人山が設置された場所は、現在の**東洞院通高辻(ひがしのとういんどおりたかつじ)と松原(まつばら)**の間ではなく、**五条通東洞院(ごじょうどおりひがしのとういん)と高倉(たかくら)**の間にありました。
現在の松原通は、当時の五条通にあたります。保昌山が最初に設置された所在地は**本燈籠町(ほんとうろうちょう)であり、そこから現在の燈籠町(とうろうちょう)**に移動したのは、**桃山時代(ももやまじだい)**の末期であるとされています。
さらに、明応(めいおう)の時期にも、依然として五条東洞院東入る町に存在していたことが、さまざまな文献によって確認されています。所在地が移動した正確な理由は明らかではありませんが、桃山時代以降、寄り町(よりまち;特定の行事や地域に関連する町)の筆頭として本燈籠町が定められたことが、この移動の背景にあると考えられています。
👉 次回予告
次回は、「室町時代の保昌山」について詳しく解説します。室町時代における保昌山の役割や、その背景にある歴史的な出来事、社会的変化について深く掘り下げていきます。お楽しみに!

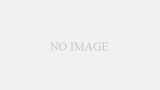
コメント