5.江戸時代中期の保昌山(えどじだいちゅうきのほうしょうやま)
🌿 黄金時代の到来と装飾の進化
**延宝(えんぽう)から安永(あんえい)**に至る50年間、**保昌山(ほうしょうやま)**は江戸時代中期において、最も華やかで豪華な装飾が施された時代を迎えました。この時期は、山鉾(やまほこ)文化の全盛期とも呼ばれる「黄金期」として知られています。祭礼が地域文化の中心として重要な役割を果たし、町衆の誇りと情熱が装飾品に表れた時代でもあります。
🎨 脛当(すねあて)の寄進
延享2年(1745年)には、浦井庄左衛門正次(うらいしょうざえもんまさつぐ)という人物が、保昌山の人形用に特別な脛当(すねあて;すねを守る防具)を寄付しました。この脛当は室町時代に作られた非常に貴重なもので、その精巧なデザインと保存状態の良さから、今日でも特別な装飾品として大切にされています。これにより、保昌山の伝統と格式がさらに高まりました。
✨ 華やかな水引の新調とその影響
寛延3年(1750年)、保昌山の**水引(みずひき;装飾用の布飾り)が新調されました。この新しい水引は、中国の明(みん)**王朝末期の刺繍技術を駆使して作られました。鳳凰(ほうおう)、鶴(つる)、龍(りゅう)、**虎(とら)**といった吉祥を象徴する動物が緻密に描かれ、特に孔雀の羽が織り込まれた部分は、見る人を圧倒する豪華さを誇ります。
この豪華な水引が目立つあまり、他の装飾品が古びて見えるようになりました。そのため、全体の調和を保つために他の懸装品も次々に新調されることになり、保昌山全体の美観が一層引き立つこととなりました。
📜 『祇園御霊会細記(ぎおんごりょうえさいき)』の刊行と装飾の進化
宝暦7年(1757年)、**『祇園御霊会細記』**という記録書が刊行されました。この書物は、各山鉾の由来や装飾品、寄り町(よりまち;支援する町)の詳細が記録されており、山鉾文化に対する関心を高める契機となりました。
この本の影響を受け、保昌山を含む多くの山鉾が装飾の刷新に取り組みました。町衆は美しさを競い合い、装飾品の完成度を高めることが祭礼に対する誇りの表現となりました。
🏯 豪華な人形装束と装飾品の詳細
-
人形:高さ約1.9メートルの立像で、**平井保昌(ひらいほうしょう)**が金色の鎧をまとい、紅梅の花を手に持っています。細部まで丁寧に作られており、祭りの中心的な存在として重んじられています。
-
御殿(ごてん):黒塗りのシンプルな構造ながらも、精緻な装飾が施されている小さな建物です。
-
水引:孔雀の羽が緻密に織り込まれた刺繍が施され、山鉾全体の豪華さを引き立てています。
-
幔幕(まんまく):雲や龍の模様があしらわれた布飾りで、祭りの神聖さと格式を強調します。
-
見送り(みおくり):赤地に花模様が施された布で、祭りの終わりを華やかに演出します。
🎨 円山応挙(まるやまおうきょ)の下絵による胴掛の新調
安永2年(1773年)、保昌山の**胴掛(どうかけ;山鉾の中央部分に掛けられる布)が新しく制作されました。このデザインは、当時名を馳せた日本画家の円山応挙(まるやまおうきょ)**が手がけました。
松屋右近(まつやうこん)と松屋勝造(まつやかつぞう)兄弟がその下絵に基づいて刺繍を施し、黒い生地に蘇武(そぶ)、鳳凰、虎、**巨霊人(きょれいじん)**などの神話的なモチーフを鮮やかに表現しました。この胴掛は、保昌山の装飾文化における新たな象徴となりました。
🏮 常飾りとしての前懸(まえかけ)の新調
**明和6年(1769年)には、金欄を使用した前懸(まえかけ;山鉾の前面に掛けられる布)**が新調されました。この装飾品は、古くなった従来の装飾品を更新する目的で制作され、祭りでの常設装飾品として活用されました。
🏆 「保昌山」の正式な名称の普及
それまで「花盗人山(はなぬすびとやま)」という俗称で呼ばれていた保昌山は、**宝暦7年(1757年)に刊行された『祇園御霊会細記』**によって、正式に「保昌山」と記録されました。
これにより、徐々に公式名称としての認知が広まっていきましたが、長年親しまれてきた「花盗人山」や「ぬいと山」という愛称も依然として広く使われ続けました。
📅 江戸時代中期の年表
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1745年 | **浦井庄左衛門正次(うらいしょうざえもんまさつぐ)**が脛当を寄進しました。 |
| 1750年 | **新しい水引(みずひき)**が制作され、装飾が一層華やかになりました。 |
| 1757年 | **『祇園御霊会細記(ぎおんごりょうえさいき)』**が刊行され、山鉾文化の装飾が発展しました。 |
| 1769年 | 金欄を使った**前懸(まえかけ)**が新調されました。 |
| 1773年 | **円山応挙(まるやまおうきょ)**の下絵による胴掛(どうかけ)が新調されました。 |
👉 次回予告
次回は、**「江戸時代末期の保昌山」**について詳しく解説します。幕末の混乱の中で、保昌山がどのようにしてその伝統を守り続けたのかをわかりやすく説明していきます。お楽しみに!

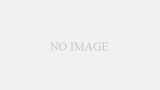
コメント