6.江戸時代末期の保昌山(えどじだいまっき)①
🔥 天明の大火と保昌山の被害
**天明8年(1788年)**の1月30日、**京洛(きょうらく;京都の古い呼び名)**で発生した大火災は、京都の町全体に壊滅的な被害をもたらしました。この火災は、当時の町家(まちや;商人や職人の家屋)のほとんどを焼き尽くし、長い歴史の中でも最も深刻な被害の一つとされています。幸いにも、**保昌山(ほうしょうやま)**の倉庫は完全に焼け落ちることなく、半焼(はんしょう)で食い止められました。しかし、損害は甚大であり、重要な装飾品や歴史的な遺産の多くが失われました。
特に残念だったのは、人形が着用していた鎧(よろい)の焼失でした。当時の記録によると、町の人々は、自分たちの家が燃えることを顧みず、保昌山の人形の頭部を収めた箱や大きな刀箱、水引(みずひき;装飾用の布)、胴幕(どうまく;装飾用の布)、**見送り(みおくり;山鉾の最後尾に掛けられる布)**など、重要な文化財を救おうと必死に動きました。しかし、**宮殿(ごてん)や鎧櫃(よろいびつ;鎧を収納する箱)**などの大きな道具類は運び出すことができず、火の手が回り、全てが焼け落ちてしまいました。
⚔️ 350年間守られてきた鎧の焼失
保昌山が創建された当初から、約350年間にわたって大切に使われ続けていたこの鎧は、鎌倉時代(1185年–1333年)に作られたとされています。この鎧は極めて精巧に作られており、特に喉輪(のどわ;喉を守る防具)、籠手(こて;腕の防具)、**胸板(むないた;胸を守る板)**といった部品には、当時の高度な技術が随所に見られます。
鎧の装飾金具の一部は後年に修復されたものもありますが、**桐の紋章(きりのもんしょう)**が彫られた金具が多く用いられていました。これらの金具は、当時の職人の緻密な技術力を示すもので、単なる装飾品以上の文化的価値を持っていました。紐や革も上質な素材が使用され、手作業による仕上げの跡が見受けられ、時代を超えてその品質が保たれていたことがうかがえます。
🔥 文化と学術における大きな損失
🌿 桐の紋が示す歴史的な意味
保昌山の装飾に刻まれた**桐の紋(きりのもん)**は、単なる美しいデザイン以上の意味を持っています。特に、足利将軍家との深い関係性を示す象徴的な存在として知られています。
桐紋は、もともと天皇家が使用していた高貴な紋章でしたが、**足利尊氏(あしかが たかうじ)が天皇から特別に授かり、室町幕府の公式な紋として定着しました。これにより、桐紋は日本の武家政権の権威を象徴するものとなりました。特に足利義満(あしかが よしみつ)**の時代には、その権威がさらに強まり、将軍家の権力を視覚的に表す重要なシンボルとなったのです。
保昌山における桐紋の使用も、足利幕府とのつながりを示唆するものと考えられます。この紋章が使われることで、保昌山は地域の歴史的な誇りを象徴する存在となり、町衆にとっても特別な意味を持つものとなったことでしょう。このように、焼失した鎧や装飾品に刻まれた桐紋は、単なる工芸品ではなく、日本の歴史と文化の連続性を示す重要な証拠として、学術的にも非常に貴重なものでした。
この鎧が失われたことは、保昌山にとってだけでなく、日本全体の文化財保護の観点からも大きな損失でした。これらの鎧は単なる装飾品ではなく、日本の武士文化や工芸技術の発展を知るための貴重な資料でした。特に、当時の技術やデザインの変遷を知る手がかりが失われたことは、学術的にも痛手でした。
🏺 焼け跡から見つかった遺品の保存と復元
大火の後、**土蔵(どぞう;土で作られた倉庫)**の焼け跡から、奇跡的に発見された鎧の破片は、学術研究において極めて重要な資料となりました。これらの破片は詳細に分析され、保存箱が用意されて、一般公開されるまでに整備されました。この保存作業は、文化財保護の取り組みの一環として、当時の技術や素材についての新たな知見をもたらしました。
以下は、焼失を免れた遺品の一部を示したものです。
残存した遺品リスト
-
一の箱
-
小田籠手(こだごて):手甲(てっこう;手を守る防具)
-
居式脛当(いしきすねあて):すねを守る防具(紺色のひもと緋色の革装飾付き)
-
-
二の箱
-
喉輪月形(のどわつきがた):喉を守る防具
-
小札(こざね):鎧の細かい部分の板、大小合わせて62枚
-
桐紋の金具装飾
-
-
三の箱
-
胸板(むないた):胸を守る部分に桐紋の装飾
-
押付板(おさえつけいた):鎧の補強用板
-
脇板(わきいた):胴体側面を守る板
-
-
四の箱
-
脛当(すねあて):すねを守る防具
-
これらの遺品は、保昌山の歴史を語る貴重な証拠となっています。
👉 次回予告
次回は、**「江戸時代末期の保昌山」**の続きを詳しく解説します。幕末の動乱の中で、保昌山がどのようにしてその伝統を守り続けたのか、文化財保護の視点からさらに掘り下げていきます。お楽しみに!

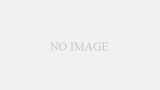
コメント