7.明治・大正時代における保昌山の修繕と保存
山飾りの修繕と新調
明治39年( 1906年 )から42年( 1909年 **)**の4年間、保昌山は装飾品の修繕に力を注ぎました。この時期、町衆の熱意と努力によって、保昌山の美しい伝統が再び輝きを取り戻しました。修繕活動は、単なる保存だけではなく、文化的な復興と町衆の誇りを示すものでした。
1️⃣ 天王人形の修繕
最初に行われたのは、天王人形の衣装と鎧(よろい)の修繕でした。この修繕は、岡田伊三郎という優れた人形師が手掛け、長年の劣化によって失われた輝きを取り戻しました。さらに、新たに装束(しょうぞく)を保管するための専用の箱も作られ、装飾品の保存状態が大幅に向上しました。
2️⃣ 金幣(きんぺい)の新調
次に、神前に掲げる金幣が新たに作られました。これは、金物を打ち込んだ蝋色(ろういろ;黒く艶を出した塗装)の棒に、緋(ひ;鮮やかな赤)の房が下げられたもので、明治41年( 1908年 **)**に完成しました。この金幣は、見た目の華やかさだけでなく、町衆の信仰心と美意識を象徴する存在となりました。
3️⃣ 神前飾りの整備
神前の飾りも徹底的に整備されました。幕は町内の有志によって寄進され、特に角田久兵衛や中埜常七ら17名が翠限(すいげん;装飾の一種)を献納しました。この整備は、町全体が協力して保昌山の文化的遺産を守ろうとする姿勢を象徴しています。
4️⃣ 太刀の修繕
明治42年( 1909年 )には、江戸時代初期に作られたとされる太刀の大規模な修繕も行われました。この太刀は、保昌山にとって重要な象徴であり、その修繕には特に精緻な技術が必要とされました。錦で包まれた柄(つか)も美しく修復され、歴史的価値がさらに高まりました。
5️⃣ 欄縁金具の修覆
最後に、欄縁(らんぶち;装飾の縁部分)の金具が全て修復されました。金具の修覆作業は、保昌山全体の装飾美を引き立たせるだけでなく、その荘厳な雰囲気を一層強調する役割を果たしました。
👉 次回予告
次回からは、**「第二章 縁起と懸装」**について詳しく解説します。保昌山の由来や伝えられてきた物語、そしてその装飾品が持つ意味や背景を紐解きながら、歴史と美の融合がどのようにして形作られたのかを、わかりやすく説明していきます。どうぞお楽しみに!

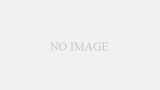
コメント