七、明治・大正時代の保昌山 🎌🏯✨
明治二年(1869年)の再興 🌟🔥🏮
保昌山が再び巡行に参加したのは、明治二年(1869年)の神事からです。幸運なことに、本飾り(山を飾る装飾品)や天王人形(祭礼に使う神像)は焼失を免れていました。本来なら、**慶応二年(1866年)**の復興と同時に巡行を再開できるはずでしたが、町内の多くの家が火災で焼けたため、三年間も山が休止していたのです。この事情から、榊(さかき)だけを巡行させる寂しい状況が続きました。
寄り町制度の廃止と補助金制度 🏘️💰📜
慶応四年(1868年)、元号が明治に改められ、維新によってさまざまな改革が行われました。山鉾文化にも変化が訪れ、従来の寄り町制度(山鉾に資金を提供する町の制度)が**明治五年(1872年)**に廃止されました。
これに伴い、各町内は**清々講社(せいせいこうしゃ)**という新しい組織を設立し、氏子(うじこ)たちから一定の神事費を徴収しました。その資金から各山鉾町に補助金が支給されることになりました。保昌山が最初に受け取った補助金は、八両(現在の貨幣価値に直せば数十万円程度)でした。
京都府からの届出命令と反発 ⚖️📑💢
明治八年(1875年)、京都府は全ての山鉾町に対して、装飾品の目録を提出するよう命じました。保昌山もこれに応じ、主要な装飾品をリスト化して報告しました。
しかし、府からの命令はそれだけにとどまりませんでした。装飾品について**「売却や質入れ(しちいれ;担保として預けること)を禁じる」**という厳しい通達も含まれていました。町家にとっては、個人資産を自由に処分できなくなるこの規制に対し、強い反発があったことが記録されています。
展示と感謝状の授与 🖼️🏅🎉
明治十年(1877年)、京都に鉄道が開通し、その開業式に合わせて開催された記念展覧会に、保昌山の装飾品が出品されました。これに対して京都府から感謝状と謝礼金が贈られ、文化財としての価値が再認識されるきっかけとなりました。
胴組の改築と装飾の修繕 🏗️🔧🎨
明治十五年(1882年)、保昌山の**胴組(どうぐみ;山鉾の骨組み部分)**は全面的に改築されました。寛政時代以来およそ100年が経過しており、耐久性の問題から改修が必要とされました。
明治三十九年(1906年)から明治四十二年(1909年)にかけて、装飾品の大規模な修繕が行われました。特に天王人形の衣装や**金幣(きんぺい;神具の一種)**が新調され、祭礼の荘厳さがさらに高まりました。
美術品としての評価 🏆🖌️📜
明治二十四年(1891年)、保昌山の装飾品が全国宝物取調局から**鑑査状(かんさじょう;美術的価値の証明書)**を受け取りました。この証明は、現在の「重要文化財」に相当するもので、以下の品々が評価されました:
- 前掛け:羊と蘇武(そぶ;中国の古代詩人)の絵
- 横掛け:白鳳凰(はくほうおう)と張騫(ちょうけん;漢代の探検家)の絵
- 横掛け:虎と巨霊人(きょれいじん;神話上の巨人)の絵
これにより、保昌山は「祭の山車」から「美術の山鉾」へと新たな評価を受けることとなりました。
年表:明治・大正時代の保昌山の主な出来事 📅📝🕰️
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1869年(明治2年) | 保昌山が巡行に復帰 |
| 1872年(明治5年) | 寄り町制度の廃止、補助金制度の導入 |
| 1875年(明治8年) | 京都府による装飾品の届け出命令 |
| 1882年(明治15年) | 胴組の全面改築 |
| 1891年(明治24年) | 全国宝物取調局より鑑査状が授与される |
| 1906年–1909年(明治39–42年) | 装飾品の大規模修繕 |
| 1909年(明治42年) | 人形所有の太刀を大修繕 |
👉 次回予告
🔮📚✨ 次回は、**「七、明治大正時代の保昌山②」**について詳しく解説します。明治から大正にかけて、保昌山がどのような変遷をたどり、その伝統をどのように守り続けていったのかを、わかりやすく説明していきます。お楽しみに!

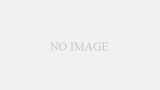
コメント