3.桃山時代の保昌山(ももやまじだい)
🌸 明応再興以後の発展
明応再興以後、装飾が整頓し華やかになったことは想像に難くありませんが、室町時代の末、いわゆる戦国時代に入ると、少しずつ衰退の兆しも見えました。しかし、織田信長や豊臣秀吉が天下統一を果たし、桃山時代に入ると、あの豪華絢爛たる文化が花盛りとなり、山鉾もまた盛運を迎え、その美観は比べ物にならないほど壮麗になりました。
この時代、織田信長が祇園会の山鉾を振興したと伝えられていますが、実際に信長が直接山鉾の再興に力を入れたわけではなく、当時の社会的背景や文化の発展が山鉾の進展を促したと考えられます。特に、信長が京都の秩序を回復したことや、豊臣秀吉による都市整備政策が間接的に山鉾文化の発展に寄与したとされています。
🏘️ 寄り町と地之口
天正19年(1591年)、豊臣秀吉が天下統一を果たすと、京都の町並みが大規模に整備されました。これに伴い、町家が急速に繁栄し、その経済的な豊かさは山鉾の装飾や規模にも大きく反映されました。この時期に定められた寄り町(よりまち)制度により、各山鉾は寄り町から地之口米(じのくちまい)と呼ばれる支援金を集め、祭礼に必要な経費を賄うことができるようになりました。また、寄り町は人足(にんそく)の確保や警護といった支援も行い、この制度はおよそ300年間にわたって山鉾文化の維持と発展に大きく寄与しました。
📜 保昌山の「寄り町」
保昌山の寄り町として定められた町は以下の八ヶ町です:
- 松原東洞院東入(まつばらひがしのとういんひがしいり) 本燈籠町 (慶長から元禄時代にかけて「紙子屋町(かみこやまち)」と称した)
- 東洞院仏光寺南入 高橋町(片原町から高橋町に改称)
- 間之町高辻下ル 稲荷町
- 松原柳馬場西入 杉屋町
- 松原寺町西入 石不動元町
- 寺町松原北入 蓮池町(明治2年から**京極町(きょうごくまち)**と改称)
- 高倉綾小路下ル 竹屋町
- 高倉四条南入 材木町(明治2年より**高材木町(たかざいもくまち)**と改称)
これらの町々は、保昌山の運営資金を支える役割を果たし、祭礼の成功に欠かせない存在となりました。
🎨 当時の装飾と文化の影響
桃山時代の保昌山は、当時の豪華絢爛な文化を反映した壮麗な装飾が施されていました。**洛中洛外(らくちゅうらくがい)**の屏風絵や古文書から推測される特徴は以下の通りです:
- 山には立派な松の木が植えられ、祭礼全体の象徴として機能しました。
- **山洞(さんどう)**は模様入りの錦織で包まれ、その装飾は非常に豪華でした。
- **水引(みずひき)**は二段にわたって掛けられ、視覚的な迫力を生み出しました。
- **胴掛け(どうかけ)**は幔幕(まんまく)風のデザインが多く用いられ、格式の高さを表現していました。
- **見送り(みおくり)**は山洞から直接掛けられ、視覚的に統一された美しい仕上がりが特徴です。
- **洞幕(どうまく)**も使用され、全体の装飾に格式と重厚感を与えていました。
これらの装飾は、当時の職人たちの高い技術と美意識を象徴しており、山鉾文化の黄金時代を築き上げたことは間違いありません。

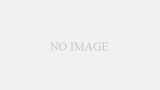
コメント