2.室町時代の保昌山(むろまちじだい)
📜 最初の文献に見られる記録
保昌山(ほうしょうやま)が最初にどのような姿であったのかは、はっきりとした記録が残っていません。しかし、**『祇園社記(ぎおんしゃき)』**に記された内容が最初の文献として知られています。
この記録によると、保昌山は**花職人山(はなしょくにんやま)**と呼ばれ、六月七日の神事の行列に加わり、巡行していたことがわかります。この記録は、保昌山が当時から重要な役割を果たしていたことを示す貴重な証拠となっています。
🔥 応仁の乱による中断
**応仁元年(1467年)に始まった応仁の乱(おうにんのらん)**は、京都を焼け野原に変える大規模な内乱となりました。この戦乱の影響で、保昌山を含む多くの山鉾は一時的に巡行が中止されることとなりました。
当時の京都は戦乱によって大きな被害を受け、街全体が荒廃してしまいました。このような状況下では、いかに壮麗な神事であっても再開は難しく、約30年間にわたって祇園会そのものが中断されることとなりました。
🌸 明応の再興
その後、**後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)**の時代、**明応5年(1496年)に足利義澄(あしかが よしずみ)**将軍によって祇園会の再興が命じられました。この再興命令により、約2~3年の間に多くの山鉾が復活し、再び華やかな祭りの光景が戻ってきました。
『祇園社記』には、応仁の乱後に再興された山鉾のうち、7月7日に巡行した17基の山鉾の名前が記されています。しかし、この中に保昌山や花盗人山(はなぬすびとやま)の名は見られません。
保昌山が再び文献に登場するのは、**明応9年(1500年)の「祇園会山鉾次第以闖定之(しんていし)」**という記録です。この中で、五番目として記載されており、**内裏ノ花ヌス人山(だいりのはなぬすびとやま)**と呼ばれ、五条東洞院(ごじょうひがしのとういん)と高倉(たかくら)の間に位置していたことが記されています。
この記録から、保昌山の再興は他の山鉾よりも少し遅れて行われたことがわかります。
🏆 最初の園番(そのばん)
再興と同時に、明応9年6月6日(1500年)、**侍所頼亮(さむらいどころ よりすけ)の家で最初の取式(しゅしき;巡行の順番を決定する儀式)**が行われました。
「園番」とは、山鉾巡行の順番を決める役職を指します。これは、祇園祭の山鉾が巡行する際の順番を、争いごとを避けるために取り決める重要な役割を担う儀式です。園番の役職は町人同士の争いを防ぐために、しばしばくじ引きで巡行の順番が決められました。
この取式では、「今度御再興已後山鉾次第町人等諍論之間闖取次第也」(今回の再興以降、山鉾の巡行順は町人同士の争いを避けるため、くじ引きで決定する)とのルールが定められました。
このときの記録によれば、保昌山は五番目に選ばれ、全体で37基の山鉾の中でも比較的良い位置を得ていました。これは、再興後の保昌山が順調に再び重要な役割を担うことを示しています。
室町時代の年表
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1467年 | 応仁の乱が勃発、保昌山も含む多くの山鉾の巡行が中断 |
| 1496年 | 後土御門天皇による祇園会の再興命令(足利義澄将軍) |
| 1500年 | 明応9年、保昌山が再興される。園番で五番目に選ばれる |
| 1500年6月6日 | 侍所頼亮の家で最初の取式が行われ、巡行順番が決定 |
まとめ
室町時代を通じて、保昌山は様々な困難を乗り越え、再興を果たしました。特に、応仁の乱という大きな試練を経て、再び祇園会の重要な一部として復活を遂げたことは、祭りの歴史における重要な転換点でした。明応の再興以降、保昌山は再びその存在感を発揮し、祭りの中での重要な役割を果たすようになりました。
👉 次回予告
次回は、**「保昌山の創建」**について詳しく解説します。保昌山がどのようにして誕生し、その背後にどのような歴史があるのかを、わかりやすく説明していきます。お楽しみに!

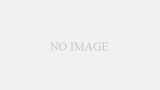
コメント