保昌山の歴史
📍 保昌山の所在地
保昌山(ほうしょうやま)は、京都市下京区にある燈籠町(とうろうちょう)に位置しています。場所は東洞院通高辻と松原通の間にあり、昔ながらの京都の雰囲気が感じられる地域です。
この山の名前は、平安時代の武士である平井保昌(ひらいのやすまさ)にちなんでつけられました。彼は、御所の庭から梅の花を折ったという逸話で知られています。実はこれは単なる盗み話ではなく、恋愛や忠誠心をテーマにした物語でもあります。そのため、京都の歴史や文化を感じさせる象徴的な出来事として語り継がれています。
昔はこの逸話があまり知られておらず、以下のような名前でも呼ばれていました:
-
花ぬす人山(はなぬすびとやま)
-
箙山(えびらやま)
-
内裏の花ぬす人山(だいりのはなぬすびとやま;内裏=天皇の住む場所)
-
花盗人山(はなぬすびとやま)
-
偷徳山(とうとくやま)
これらの名前は、地域の文化や伝説が反映されたもので、地元の人々にとっては親しみのあるものでした。
🏯 町名の由来と変遷
保昌山があるこの場所の名前は、**平重盛(たいらのしげもり)が建てた燈籠堂浄教寺(とうろうどうじょうきょうじ)**からきています。昔から信仰の中心地であり、地域の人々にとって大切な場所でした。
明治時代の前は、このエリアは**下京巽十一丁組(しもぎょうたつみじゅういっちょうぐみ)に属していました。現在は下京第十二学区(豊園学区)**となり、今でも地域の文化や伝統が息づいています。
🔄 保昌山の移動と名称の変化
室町時代には、保昌山は現在の燈籠町の隣、松原通東洞院と高倉の間(現在の本燈籠町)にありました。ここは当時、多くの人が集まり、商業や文化の交流が盛んな場所でした。
桃山時代になると、現在の燈籠町に移動したと考えられています。移動後、保昌山は地域の人々の生活に溶け込み、町のシンボルとして親しまれるようになりました。
**正徳3年(1713年)に書かれた『滑稽雑談(こっけいざつだん)』で、初めて「侯昌山」という表記がされましたが、その後も長く花盗人山(はなぬすびとやま)**と呼ばれ続けました。
宝暦7年(1757年)に出た『祇園御霊会細記(ぎおんごりょうえさいき)』では、正式に「保昌山」と記され、この名前が定着しました。明治維新以降は「花盗人山」という呼び名が避けられるようになり、正式に保昌山と呼ばれるようになりました。
それでも、地元の人たちは親しみを込めて今でも「花盗人山」と呼ぶことがあります。
📅 名称の変遷一覧(西暦変換済)
| 名称 | 年次(西暦) | 出典文献 |
|---|---|---|
| 花ぬす人山 | 1168年 | 祇園社記 第十五 |
| 内裏ノ花ヌス人山 | 1499年 | 祇園社記 第十五 |
| 内裏ノ花ヌス人山 | 1500年頃 | 藤門雑抄 |
| 花盗人山 | 1674年 | 祇園会山鉾考 |
| 花ぬす人山 | 1681年 | 祇園御本地 |
| 花盗人山 | 1707年 | 華洛細見図 |
| 花ぬす人山 | 1694年 | 洛中洛外手引案内 |
| 花盗人山 | 1713年 | 女源氏教訓鑑 |
| 保昌山 | 1713年 | 滑稽雑談 |
| 保昌山 | 1757年 | 祇園御霊会細記 |
| 箙山(えびらやま) | 1757年 | 祇園御霊会細記 |
| 花盗人山 | 1780年頃 | 雑色文書、山鉾由来 |
| 保昌山 | 1806年 | 増補祇園会細記 |
| 保昌山 | 1809年 | 保昌山宮殿の漆銘 |
| 保昌山 | 1818年 | 全天王台の墨銘 |
| 保昌山 | 1824年 | 祇園神祭山鉾銬附記 |
| 保志やう山 | 1845年 | 祇園会山鉾見物独案内図 |
| 保昌山 | 1864年 | 元治大火罹災報告書 |
| 花盗人山とも云 | 1890年 | 京都祇園会十七日山鉾図 |
| 保昌山 | 1891年 | 下京区長へ届出文書 |
| 偷花山 | 1716年 | 祇園祭会図偈引 |
📝 まとめ
保昌山は、ただの祇園祭の山鉾ではなく、京都の歴史や文化に深く関わる存在です。その名前の移り変わりは、京都という町がどのように変化し、発展してきたかを知る手がかりにもなります。
👉 次回予告
次回からは、保昌山の**「起源(きげん)と沿革(えんかく)」**について詳しくご紹介します。
保昌山がどのように生まれ、どのような歴史を歩んできたのか、その秘密に迫ります!お楽しみに!

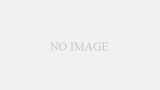
コメント