縁起(えんぎ)
平井保昌(ひらい やすまさ)
平井保昌は、藤原大納言元方(ふじわら だいなごん もとかた)の孫であり、父は致忠(むねただ)、母は**允明親王(いんみょう しんのう)の子孫と伝えられています。
彼は智勇(ちゆう;知恵と勇気)**に優れ、武芸にも秀でており、**和歌(わか;日本の伝統的な短歌)にも才能を発揮しました。官職は丹波守(たんばのかみ;丹波国の長官)**にまで昇進し、**源頼光(みなもとのよりみつ)の四天王(してんのう;特に優れた4人の武将)**の一人として広く名を知られています。
保昌の恋物語
ある日、保昌は宮中の女性に恋心を抱き、手紙を送りました。女性は「本当に私のことを思っているのなら、**南殿(なんでん)**の梅の花を折ってきてください」と難題を出しました。
保昌はその願いを叶えるため、密かに宮中に忍び込み、**紫宸殿(ししんでん;天皇が儀式を行う場所)**の前に咲く梅の花を折って贈ったとされています。
その女性は、後に有名な**和泉式部(いずみしきぶ)であり、彼の妻となりました。この逸話が保昌山(やすまさやま)**の縁起とされ、人形や飾りもこの伝説に基づいています。
「縁起」とは、物事の起こりや由来を説明するものです。
現代では「運が良いこと」や「良い兆し」の意味で使われることもありますが、本来は、出来事がどのように始まったのか、背景にどんな歴史があるのかを説明する言葉です。
異説(いせつ)
保昌五郎説(やすまさごろう せつ)
一部では、保昌五郎という人物が宮中に忍び込んで梅の花を盗んだという説も存在しました。この説は、延宝元年(えんぽうがんねん;1673年)に著された『山師考(やましこう)』や正徹3年の『滑稽雑談(こっけいざつだん)』に記録されていますが、後に正式な説として平井保昌の話が広まると、この異説は廃れていきました。
梶原景季説(かじわら かげすえ せつ)
また、**梶原源太景季(かじわら げんた かげすえ)が源平合戦(げんぺいがっせん)**の際、**一ノ谷(いちのたに)**の戦いで梅の枝を折り、**箙(えびら;矢を入れる道具)**に挿して戦ったという説も存在します。しかし、この説は山鉾(やまぼこ)の飾りと一致しない部分が多く、後に廃れていきました。
熊谷直実説(くまがい なおざね せつ)
さらに、江戸時代の文書においては、**熊谷次郎直実(くまがい じろう なおざね)**が、源義経(みなもとの よしつね)とともに一ノ谷に向かう途中、**祇園社(ぎおんしゃ)**で花を折ってお守りにしたという説もあります。しかし、この説は史実の裏付けが薄く、民間伝承の一部にとどまっています。
📅 年表:保昌山にまつわる説の流れ
| 名前 | 年代 | 出来事 |
|---|---|---|
| 平井保昌 | 18世紀(江戸時代中期) | 『祇園御霊会細記(ぎおんごりょうえさいき)』にて、正式な縁起として掲載される |
| 保昌五郎 | 1673年(延宝元年) | 『山師考(やましこう)』において、梅の花を盗む説が記される |
| 梶原景季 | 1673年(延宝元年) | 『祇園会山鉾考(ぎおんえやまほここう)』で、箙の梅の故事に基づく説が登場 |
| 熊谷直実 | 18世紀末(寛政年間) | 江戸時代の文書に、祇園社で花を折る伝説が記録される |
👉 次回予告
次回は「第二章 縁起と懸装」の人形編をお届けします。それぞれの時代背景を映し出す人形たちは、どのように当時の文化や風習を表現しているのでしょうか。歴史の息吹を感じながら、保昌山の奥深い魅力に迫っていきます。お楽しみに!

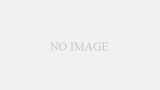
コメント