6.江戸時代末期の保昌山 — 六年間の休止と復興②
🔥 天明の大火と六年間の休止
天明8年(1788年)、京都を襲った天明の大火は、祇園祭(ぎおんまつり)の運営に深刻な影響を及ぼしました。この年の祭礼では、例年通りの盛大な神事が行われることはなく、辛うじて焼失を免れた**七基の山鉾(やまほこ)**だけが巡行するという、非常に縮小された形での開催となりました。鉾町では、装飾品の一部を町内に飾ることで神事を簡素に執り行い、伝統を途切れさせないための努力が続けられました。しかし、**保昌山(ほうしょうやま)**は、被害が甚大であったため、祭礼への参加を見送ることとなり、町衆にとって大きな失望となりました。
その後の6年間、保昌山は巡行に参加できず、焼け野原となった町内では、復興に向けた準備が粛々と進められていました。町人たちは、山に飾られる人形(にんぎょう)や宮殿(きゅうでん)、そして**胴組(どうぐみ;山鉾の骨組み)**の修復に向けて少しずつ資材を集め、伝統を再興するための道のりを歩み始めたのです。こうした地道な努力の積み重ねが、最終的に保昌山の復帰への道を開きました。
🔄 寛政時代の復興
寛政元年(1789年)、他の山鉾である占出山(うらでやま)、山伏山(やまぶしやま)、霰天神山(あられてんじんやま)、**芦刈山(あしかりやま)**などが巡行を再開しました。これらの山鉾が復活することによって、町衆の士気も高まり、保昌山の再建に向けた動きも本格化していきました。
**寛政5年(1793年)には郭巨山(かっきょやま)**も復興を果たし、周囲の町家もこれに刺激を受け、祭りに対する熱意を再燃させました。保昌山に関わる町衆たちは、再建に向けて日々努力を重ね、失われた文化を復活させるための準備を着々と進めていきました。
そして、ついに寛政6年(1794年)、保昌山は**岩戸山(いわとやま)**と共に巡行へ復帰を果たしました。当時の記録『児本並子息出勤之記』には、
「当年白楽天 保昌山 岩戸山 出ル」
と記されており、これが町全体にとっていかに大きな喜びと誇りの瞬間であったかが伝わってきます。
🏯 宮殿の新築
復興にあたって最初に行われたのは、失われた胴組の修繕です。これは山鉾の基本構造であり、その修復がなければ山自体を建て直すことは不可能でした。そして次に着手されたのが、**宮殿(きゅうでん;神の依代となる建物)の新築工事です。新しい宮殿は、従来の流れ造り(ながれづくり;屋根が片流れになった神社建築様式)から、より格式の高い入母屋造り(いりもやづくり;屋根の両側が斜めに傾斜した様式)**へと改められました。
この新築工事を担当したのは、京都の宮殿師**竹内平四郎(たけうち へいしろう)で、寛政6年(1794年)5月に完成しました。当初は白木(しらき;塗装されていない木材)のまま使用されていましたが、装飾の完成は文化2年(1805年)**に持ち越され、より一層の荘厳さが加わることとなりました。
👤 人形の修復と勇祐の功績
保昌山の象徴である人形の修復は、復興の中でも特に重要な事業でした。とりわけ、人形の**体躯(たいく;胴体部分)の彫刻は、当時名工として知られた勇祐(ゆうすけ)によって手がけられました。勇祐は慎重に過去の資料を調査し、かつての像の姿を忠実に再現するために、まず1/10サイズの雛型(ひながた)**を作成しました。この雛型をもとにして本像が完成され、その完成度は非常に高く、かつての姿そのままに蘇りました。
奇跡的に大火から免れた首部分はそのまま利用され、新たに彫刻された胴体と組み合わされることで、かつての威厳と美しさを取り戻しました。この雛型は後に記念として**川島喜助(かわしま きすけ)に贈られ、最終的に明治23年(1890年)**に保昌山に寄贈され、今日に至るまで大切に保存されています。
🏯 明智十次郎の鎧
修復された人形には、明智光秀(あけち みつひで)の嫡子明智十次郎光慶(あけち じゅうじろう みつよし)が実際に使用したと伝えられる鎧(よろい)が着せられました。この鎧は、京都の大善院(だいぜんいん)から寄進されたもので、金色の小札(こざね;鎧の小さな板)と鮮やかな緋色(ひいろ)の装飾が施されています。
大善院は、かつて**祇園御旅所(ぎおんおたびしょ;祭礼で神輿が一時的に安置される場所)**の管理を担っており、その関係から祭礼に必要な甲冑を多く所蔵していたと考えられます。この華麗な鎧は、保昌山にさらなる華やかさを与え、その復興に際して重要な象徴となりました。
📅 江戸時代末期の保昌山 — 年表
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1788年(天明8年) | 天明の大火により保昌山が焼失。6年間の祭礼休止が始まる。 |
| 1789年(寛政元年) | 他の山鉾が順次巡行を再開。保昌山は復興準備を進める。 |
| 1794年(寛政6年) | 保昌山が巡行復帰。宮殿と人形が新たに修復される。 |
| 1805年(文化2年) | 宮殿に塗装が施され、完全な形で装飾が完成。 |
| 1890年(明治23年) | 川島家から人形の雛型が寄贈され、保昌山の歴史的遺産として保存される。 |
👉 次回予告
「江戸時代末期の保昌山」の最終回では、いよいよ保昌山がどのようにして現代に至るまでその伝統を守り続けたのか、その最後の復興と近代への移行を詳しく解説します。お楽しみに!

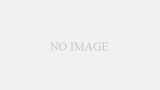
コメント