6.江戸時代末期の保昌山 (えどじだいまっき)③
🌟 寛政の出山(かんせいのでやま)
寛政6年(1794年)、長らく休止していた**保昌山(ほうしょうやま)が、ついに山鈴行列(やますずぎょうれつ;山鉾巡行の順番表)**に再び名を連ねることとなりました。6年間にわたる休止期間の間、町民たちはこの伝統の再興に向けて多大な努力を続けてきました。その尽力が実を結び、ついに保昌山は再びその美しい姿を現すことができたのです。この復活は、京都の祭礼文化における一大イベントとなり、多くの町民たちの心に深い感動を刻みました。保昌山の復活は、京都の誇りを象徴する出来事であり、地域社会の連帯と伝統継承の大切さを改めて強調しました。
📜 雑色の山鉾由来(ざっしょくのやまほこゆらい)
江戸時代を通じて、**山師(やまし;山鉾の管理者)のもとで記録されていた文献の中に、『山鉾由来(やまほこゆらい)』という重要な書物があります。この文献は寛政初年(1789年頃)に記されたもので、当時の保昌山は「花盗人(はなぬすびと)」**と呼ばれていました。この名前は、華やかで目を引く装飾が、まるで人々の心を盗んでしまうかのような魅力を放っていたことに由来します。この呼び名は、江戸時代の町民たちの間でも親しまれており、保昌山の伝統的な文化的価値を象徴するものとして長く記憶され続けました。
🎨 見送りの新調(みおくりのしんちょう)
寛政10年(1798年)、保昌山の復興から5年が経過したこの年、山鉾の背面装飾である**見送り(みおくり)**が新たに制作されることとなりました。この新調された見送りは、**三星図(さんせいず)と呼ばれる仙人寿星(せんじんじゅせい)**の模様が施されており、その優雅さと格式の高さは、当時の最高峰の技術を象徴しています。制作にあたった絵師の名は記録されていませんが、その緻密な織物技法と精巧なデザインは、町民たちの誇りを一層高めるものとなりました。地域の協力と支援を得て、この見送りは保昌山の美しさを引き立てる重要な要素として、町全体の誇りと団結を象徴する存在となりました。
🏯 宮殿の塗装(きゅうでんのとそう)
文化2年(1805年)には、長年白木(しらき;無塗装の木材)のまま使用されていた宮殿が、漆塗り(うるしぬり)によって新たに美しく仕上げられました。この漆塗りは、名工**河内屋九兵衛(かわちや きゅうべえ)**によって施され、その艶やかで光沢のある仕上がりは、保昌山の荘厳さと格式を一層際立たせました。この修繕によって、宮殿は単なる装飾以上の象徴的存在となり、保昌山の歴史的意義とともに後世に受け継がれることとなったのです。
🎭 文化時代の装飾(ぶんかじだいのそうしょく)
**文化9年(1812年)に記された『増補祇園会細記(ぞうほぎおんえさいき)』**には、保昌山の当時の装飾について詳しく記述されています。この記録によると、保昌山の装飾は以下のような特徴を持っていました:
-
御殿:本物の松の木の左側に設置され、祭礼における神聖さと格式を象徴しました。
-
押縁(おしぶち):黒塗りの装飾に金具が施され、その上品さと格式が強調されました。
-
水引(みずひき):鳳凰(ほうおう)や麒麟(きりん)の模様が織り込まれ、豪華で壮麗な装飾美を表現しました。
-
金幣(きんぺい):四方に配置され、山鉾全体の荘厳さを一層際立たせました。
-
見送り:精緻な織物によって表現された人物図が特徴であり、当時の職人技術の粋が込められた作品でした。
⚔️ 文政期の修繕(ぶんせいきのしゅうぜん)
**文政元年(1818年)**には、**天王台(てんのうだい;神輿を置く台座)**が新たに製作されました。この天王台は、保昌山の装飾品の中で初めて「保昌山」の名が明記された重要な品となりました。同時期には、見送り掛けも新たに作り直され、全体の装飾がこれまで以上に豪華に整えられました。
🎭 文政時代の装飾
特徴は以下の通りです:
-
御殿:東洞院高辻下ル町に設置され、町内の誇りとされました。
-
金幣:四方に配置され、山鉾全体の荘厳さを高めました。
-
水引:折敷錦(おしきにしき)の技法で孔雀(くじゃく)や鳳凰(ほうおう)の丸模様が施され、華麗な装飾美を表現しました。
-
下水引:花色の組糸によって輪違いの房飾りが作られ、祭礼に彩りを添えました。
-
胴幕:猩々緋(しょうじょうひ;鮮やかな赤色)で仙人の模様が織り込まれ、その鮮やかさが一層際立ちました。
-
見送り:寿老人(じゅろうじん)や婦人が描かれた精緻な織物が施され、当時の職人技術が存分に発揮された逸品となりました。
🔥 元治の戦禍と修復(げんじのせんかとしゅうふく)
元治元年(1864年)、禁門の変(きんもんのへん)という大きな戦火が京都を襲い、数多くの山鉾が被害を受けました。保昌山もその例外ではなく、特に雨具(あまぐ)や冑飾(かぶとかざり)などの貴重な装飾品が焼失してしまいました。しかし、町民たちの迅速な対応と献身的な努力によって、人形や本飾りといった重要な品々は守られることとなりました。この迅速な対応により、伝統の火を絶やすことなく守り抜くことができたのです。
🎲 文政期の籤番(くじばん)
江戸時代の山鉾巡行では、毎年の巡行順序を決定するために**籤番(くじばん)**が設けられていました。保昌山もこの制度に従い、順番に巡行する役割を担っていました。特に文政期以降の記録では、保昌山の巡行順が以下のように記されています:
-
安政6年(1859年):五番
-
万延元年(1860年):一番
-
文久元年(1861年):七番
-
文久2年(1862年):十二番
-
文久3年(1863年):十番
-
元治元年(1864年):十三番
このように、保昌山は時期によって巡行の順番が変わり、その年ごとの籤引きによって祭礼の役割が決められていました。この制度は、公平性を保ちながらも、祭礼の緊張感と期待感を高める重要な役割を果たしていたのです。
元治元年(1864年)、禁門の変(きんもんのへん)という大きな戦火が京都を襲い、数多くの山鉾が被害を受けました。保昌山もその例外ではなく、特に雨具(あまぐ)や冑飾(かぶとかざり)などの貴重な装飾品が焼失してしまいました。しかし、町民たちの迅速な対応と献身的な努力によって、人形や本飾りといった重要な品々は守られることとなりました。この迅速な対応により、伝統の火を絶やすことなく守り抜くことができたのです。
📅 江戸時代末期の保昌山 — 年表
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1794年(寛政6年) | 保昌山が山鉾巡行に復帰。 |
| 1798年(寛政10年) | 見送りが新調される。 |
| 1805年(文化2年) | 宮殿が漆塗りで美しく仕上げられる。 |
| 1818年(文政元年) | 天王台の新調と見送り掛けの刷新。 |
| 1864年(元治元年) | 禁門の変による被害を受けるが、主要な装飾は守られる。 |
👉 次回予告
次回は、**「明治・大正時代の保昌山」**について詳しく解説します。近代化が進む中、保昌山がどのようにしてその伝統を守り続けたのか、新たな挑戦と変化をわかりやすくお届けします。お楽しみに!

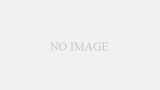
コメント